■ 豊永酒造ご紹介
「清流はやがて球磨の銘酒となる」
急流の球磨川を遡ると山のふところ奥深く熊本県・球磨盆地があります。この球磨川に沿って走る国道219号線沿いには29軒の球磨焼酎蔵があります。豊永酒造さんは、その中でも山地より、人吉市内から車で30分程の湯前町の静かな街中にあります。球磨焼酎屋の赤レンガ造りの煙突は、蔵の廃業や近代化でだいぶ少なくなりましたが、豊永酒造さんには古い赤レンガ造りの煙突と今では珍しい「石室」(〜いしむろ〜石の壁でできている麹室)が残っています。現在は4代目当主・豊永 史郎さんが社長兼杜氏として造りの前面に立っておられます。豊永さんは「土造りから始める有機農法」に早くから注目し農家の方々と共に歩んできました。2000年には厳しい条件をクリアして、全ての契約農家が「無農薬」の認定を受けただけでなく、豊永酒造さんのお蔵自体も「無農薬」の認定を受けました。豊永 史郎さんの環境問題への熱い取り組みが伝わります。「焼酎メーカーである以上、農業とそれを取り巻く環境問題に関わることは当然です。地元の農家の皆さんと共存しなくては…。農家の皆さんは『豊永の酒が売れなかったら米のせいだから、頑張って米を造る』と言ってくれるし…僕も『このいい米を無駄にしてはいけない』といつも思っています。でも、あまり農業のことを前面に出して焼酎の宣伝にしたくない。ごくごくあたり前の事として関わってゆきたい。」自分の由とする「造り」にこだわり、新しいものにも挑戦しますが、本物しか認めない厳しい姿勢をもつ九州男子です。現在600石(1升ビン6万本程度)の年間生産量で、焼酎業界からみれば小規模な蔵元ですが豊永 史郎さんのお人柄、焼酎に対する姿勢・酒質は各方面から高い評価を得ています。「これ以上大きくならなくていいんです。大きくなって大切な人達〜農家・酒屋・愛飲家〜と距離をおきたくない。」自分が納得できる米焼酎は、なるべく顔の見える人に飲んでいただきた。そのためにもう少ししぼって小さくなろうと思っています。電話には必ず私か嫁さんがでるような…そんな蔵を目指します。やっと考えがまとまったので、その意味も込めて酒名を変えました。」豊永 史郎さんは西暦2000年の自らの社長就任を機に、慣れ親しんだ「遼山」から「豊永蔵」へと酒名を変更しました。豊永さんの決意の固さが伺われます。豊永さんの焼酎造りの基本は「球磨の原料・水を使い、球磨の人の手で醸された酒」です新しい挑戦として、「焼酎好適米(しょうちゅうこうてきまい〜焼酎造りに適したお米〜)を造る」こと、「手造りの原点を目指すこと」を掲げてより小さい仕込みを始めました・「洗米(せんまい)」にすごく時間をかけています。周りからは馬鹿に見えるかもしれませんが…。伝承の造りを通して新しい味・旨味・まろやかさを表現できれば…」と語っています。近頃の「本格焼酎ブーム」に流されず、しかし単なる保守的な造り手ではない豊永さん。かれが醸す「豊永蔵」や「観無量」・「完囲い」が球磨焼酎を代表する銘酒になることは間違いありません。
 |
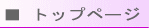 |