■富田酒造ご紹介
奄美大島にただ一軒、昔ながらの甕仕込みをしている焼酎屋がある。 富田酒造場の従業員は兄弟4人。島でいちばん小さな酒造である。「手をかければかけるほど、思いが伝わるような気がして。生きものだからでしょう、応えてくれんです」 兄弟が幼い頃、麹作りをしていたおふくろさんは、麹室に入ると、ご飯の支度以外には出てこなかった。幼い頃「焼酎と子供とどっちが大事?」と聞いた息子たちが、今は一切を取り仕切る。 蒸し米に黒麹を打って麹を作り、水とともに3石甕に仕込む。人間が立って湯浴みできるほどの深さがある大甕だ。
1週間ほどしたら、溶かした黒糖を2次仕込みする。アルコール発酵をする酵母たちの餌である。「黒糖の甘さは、酵母たちが食べてしまうから、味には出てきません。ほのかに香りが残る程度です」 毎日1回櫂を入れ、仕込んで2週間で10度から15度の酒になる。 これを蒸留して、半年から1年熟成させると焼酎になる。蒸留器から最初に出てくる初酒は、ハナザケと呼ばれる。アルコール度70度、甘く熟した熱帯果実のような香気のある酒で、酒造家でなければ味わえない至福である。 酒造りは気温に大きく左右さえる。発酵にたずさわる微生物たちは暑すぎても寒すぎても元気がない。夏場3ヶ月は休み。春と秋は機嫌がよく、酒のできもいいそうだ。 彼らの好む気温を保つために、奄美の焼酎甕は半分土中に埋めてある。沖縄では地上に、奄美より寒い鹿児島ではすっぽり土に埋まっている。
「同じ日数でも、外気の影響を受ける窓際の甕は発酵が遅いんですよ」
「甕のくせも全部わかっているから愛着がわいてね」 ひとつひとつの甕にさわって、40年間焼酎造りにたずさわってきたおふくろさんはいう。
価格面で勝負にならない。経営が行き詰まって、このままであと1年待つかというとき、最後の大盤振舞するつもりで、採算も取れない特上の酒を造った。これが思いがけずすぐに売れ切れた。
「製法を見ていなくても、いい酒を造れば飲む人はわかってくれる」 もっといい酒にして応えなければと、そのとき最後の一軒になっても甕仕込みでいく腹を決めた。 島に吹く風の冷たさや土の温もり、わずかずつでも息をする甕に抱かれて醸されるおおらかな酒こそ、島んちゅの酒である。 泉重千代さんが最後まで愛飲していたのは、富田兄弟の甕仕込みだったそうだ。
(サライ1997年5月号/文・陸田 幸枝様より引用しました)

|
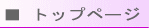 |