■ 谷口酒造ご紹介
「東京の本格焼酎見つけた!」
それは平成13年3月8日の午後2時過ぎのことです。私が配送するお酒の荷造りに追われていると、店の前に中をうかがう男の人がいました。「また、谷中のお寺巡りの人だな…古い酒屋だから」と思ってそのままにしておきました。一度姿が見えなくなったと思ったら、また暫くすると店先にいてこちらをみています。一見すると東京芸術大学(すぐ近くにあります)の美術関係の人っぽい雰囲気を漂わせていました。やがて店に入ってきて「あのー私…、伊豆大島で焼酎を造ってるんですけど…あっ、売り込みとかじゃなく、ちょっと飲んで欲しいと思って…大島で1軒だけなんで自分で造った焼酎がどんなもんか解らなくて、それでお酒をみてもらおうと思いまして…」と言うではありませんか。それが私と谷口 英久さんの出会いでした。
10日ほど過ぎた3月21日、私は伊豆大島空港に降り立っていました。店先で話したことが気になって、ついつい来てしまったのです。伊豆大島では最後に残った蔵元であること、38歳の谷口さんが一人で醸していること、島外の焼酎が入ってきて市場が変わってきていること等など、そして試飲させてもらった麦焼酎が甘み・旨味のある酒だったことです。
「えっ、東京の焼酎?」と思われるかもしれませんが、八丈島を始めとする島酒の歴史は古く、江戸時代に薩摩より蒸留機が伝来して以来です。日頃から南九州の地、風俗、民俗が深く結びついた「本格焼酎」に憧れる私としては「いつかは地元の酒を売りたい」という強い願望がありました。「おいおい、島も地元かよ?」と思うかもしれませんが、はっきり言って「私の思い込み」です。それでいいんです。
果たして谷口さんにその「背景」となるものはあるのかまず自分の目で確かめたい気持ちでした。大島空港から車で20分弱ほどの所に蔵元があります。この蔵元の事務所がまず変わっていました。
外見は「ムーミン谷の仲間達」風で土壁で仕上げた塔を思わせ、おまけに屋根のてっぺんに椿の花が一輪植えてあります。中に入ると「ゲゲゲの鬼太郎」風の中二階がある木造の造りになっています。谷口さんは大学卒業後、美学校で文筆に励みライターを目指していたそうです。家業を継ぎ3代目蔵元として本格焼酎造りを本業とした現在でも、関東限定月刊誌「散歩の達人」で『1円大王』を連載しています。奥様と二人三脚で、「造り」から始まり蔵のほとんど全ての工程をこなしています。製造石数(1石は1,8L瓶100本)は130石前後と小さな蔵元ですが、「いいんです。今の造り・味わいをもっと深めたいし、今の時点で量を追えば必ず品質が下がります。人を使えば可能でしょうが、私は一人で納得がゆく様にやりたいんです…。」と谷口さん。その顔には力みもなく、肩に力を入れすぎでもないし諦めている訳でもない。ただ、「自己表現」「作品」としての焼酎を納得がゆくまで深めたい、それを世に問うてみたい、そんな感じでしょうか。
「島では甲類焼酎やライトなものが支持されています。自分が良しと思う酒がなかなか解ってもらえない。」
そんな素直な気持ちを淡々とそして少しシャイな笑顔で話してくれました。伝統的な手法(常圧蒸留)で醸される谷口さんの麦焼酎は甘く香ばしい味わいですが、ライトタイプ主流の島内ではそれだけで瓶詰めされることなく、口当たりの良い軽いタイプ(減圧蒸留)のものとブレンドされていました。
「ブレンドも飲みやすくていいけど、これは単独で瓶に詰めてもいいんじゃないですか…」と私が問うと谷口さんの顔がほころびました。どうやら私の「地元の酒」を発見した瞬間でした。

|
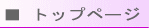 |