■ 田村合名ご紹介
「女性蔵元が織りなすの珠玉の酒」
鹿児島市内より錦港湾の海岸線沿いに車を走らせ80分程、「甕壷仕込み 純黒」の製造元・田村合名は薩摩半島の最南端・鹿児島県揖宿郡山川町にあります。静かな海岸のすぐ近く、海では魚の姿も見ることができ、開聞岳に連なる山々の緑が濃い風光明媚な田舎町です。山川町は昔から鰹(かつお)遠洋漁業の基地であり、「鰹節」の名産地として広く知られています。また、近くには明治維新の英雄・西郷さんが愛した名湯・「鰻温泉」(うなぎおんせん)がや、全国的に有名な「砂風呂」があり、年平均気温が18度という温暖な気候に恵まれています。この街は、前田 利衛門が琉球(沖縄県)から初めて「唐芋」(からいも〜今でも薩摩芋を鹿児島ではこう呼びます〜)を持ち帰った伝来の地であり、芋焼酎とは」縁の深い土地柄です。海まで数十歩、潮風にさらされたレンガ造りの煙突がお蔵の目印になっています。このお蔵のご主人・桑鶴 ミヨ子さんは県内でも数少ない女性のお蔵元です。田村家に嫁いで、早くにご主人を亡くされたそうですが、義理のお母様から「あんたしかこの蔵を守れるモンはおらん!」と説得され、それ以降女性の細腕で頑張っておられます。「私は運がついている。ラッキーガールなんよ。」と笑ってお話になりますが、お言葉のに通り桑鶴 ミヨ子社長が復活された「甕壷仕込み」で醸す「純黒」はお蔵の看板のお酒となり、銘醸として全国に知られる様になっています。お蔵に入ると44個の甕がところ狭しと並んでいます。いったんは使われなかった甕ですが保管の状態が良かったため、今でも明治創業以来の甕が使われています。「この辺りは、2メートルも掘れば温泉が涌く」ということで、地熱の関係でどの甕壷も他のお蔵に比べ、あまり地中に埋め込んでありません。焼酎の製造過程で「醪(もろみ)」の発酵温度が上がりすぎてしまうからです。この場所であえて「甕仕込み」に取り組み、レギュラー品も「一次仕込み」は全て甕で行うところに桑鶴社長のこだわりが感じられます。もうひとつこのお蔵の特徴は、惜しくも先年造りの現場を退かれた黒瀬杜氏・宿里清一郎さんの存在です。焼酎造りで数々の名人杜氏を生んだ「黒瀬杜氏(くろせとじ)」は鹿児島県笠沙町黒瀬という集落の出身の方達です。村には僅かな農地しかなく、焼酎造りの仕事で得る収入は欠かせないものでした。そこで、「造り」に関する技術を親子・兄弟、同じ村出身の人だけに伝え、外に洩らさぬ様にしたことが「黒瀬杜氏」という技能集団を生んだのです。近年は例にもれず「黒瀬杜氏」の数も減り、その存続が危ぶまれています。宿里さんご自身も70歳を超えられて「顧問」という形でここ数年「造り」に携わっておられましたが、杜氏歴四十数年の経験と伝承の技は今も若い蔵人達に受け継がれ、このお蔵の大きな支えになっています。宿里さんご自身も最初は「一次仕込みだけでも大変なのに、二次仕込みまで甕で出来るだろうか…」と思われたそうですが苦労の末完成され、桑鶴社長の期待に見事応えたお酒が「甕壷仕込み 純黒」です。また、お蔵では白麹・黒麹・黄麹でそれぞれのお酒を造り、「薩摩乃薫」・「純黒」・「鷲尾」(わしお)の名で発売されています。麹(こうじ)による味の違いや個性の差を的確に表現し、飲み手に伝える技術には感嘆させられます。
芋焼酎の奥深さ・伝承の技を感じることが出来る県内屈指の銘醸といえます。

|
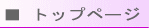 |