■ 高良酒造ご紹介
「芋焼酎の原風景・原点を感じる屈指の銘醸」
鹿児島市内から車で40分ほど走った川辺郡の田園風景の中に高良酒造がある。川辺は昔から伝説に語られるほど、水と田畑・穀物の実り豊かなところ。そして、旨い焼酎の出来るところであった。このお蔵には、薩摩焼酎の原風景が残っている 。仕込み蔵の前にある木造の母屋、右手に広がる芋畑、裏庭の池には飯倉山の地下水が湧き出している。この清水は仕込みや割水(わりみず)にふんだんに使い、焼酎造り〜『田倉』(たくら)・『八幡』〜にとってかけがいのない水なのだ。池に浮かぶ苔むした岩の上に「水神様」が祭られている。暮れについた餅や節句の祝菓子等折につけ「水神様」にお供えをするのはこの家の女性の役目なのだそうだ。4代目当主の高良 武信氏が現在は杜氏を努める。朴訥(ぼくとつ)だが、笑顔を絶やさず、芯の強さを感じる薩摩男子。見通しにきく「等身大の自然」と向かい合いながら代々受け継がれた「半農半酎(夏は農業・冬は焼酎造り)」の生活を送っている。焼酎造りにおいては「甕仕込み」にこだわり、あるがままの環境で昔ながらの手造りを大事にしている。この風景・高良さんの「焼酎造り」に対する姿勢こそ芋焼酎蔵の原点であり、私が薩摩を感じることができる数少ない造り手である。池の周りに咲く「卯の花」が盛りが過ぎ、お盆が終わるとそろそろ蔵は忙しくなる。原料となる芋は新鮮なものに限る。そこで、近在の農家10軒ほどと契約し、、毎日掘り立ての芋を持ってきてもらっている。その日仕込む分の芋は、その日の朝に準備する。一家総出で皮を剥く。急ぐとはいえ、芋を持つ手はそっと卵を持つ様に優しい。ほんのちょっとした傷(きず)が焼酎の香りを壊してしまうからだ。「自然の営み」は想像以上に微妙なものである。家族が手伝うといえども男手一人の焼酎造りは過酷そのものだ。強い意志とたぎる情熱がなければ、3ヶ月に及ぶ不眠不休の働きは出来ない。「麹(こうじ)」を育てる夜は何度も起きて温度・湿度に気を配り、芋集荷の時はトラックに乗って芋畑を走り、30kg入りの芋袋と泥だらけの大格闘!これも、夏場に百姓仕事で鍛えた体だからこそ…
年末ようやく酒造期も終わり近くなると、ゲッソリ痩せて髭ボウボウ。
その瞳だけが満足の微笑みをたたえる…まさに「男の魂の酒」!!
今宵は、じっくりこのピュアな芋の風味をお楽しみください。!!
 |
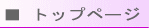 |