■ 岩倉酒造ご紹介
「おいしい焼酎は『家族会議』から
宮崎県西都市、澄んだ空気そして濃い緑が広がる。何処にでもある、のどかな田舎だがふと気づくと畑の中に小さな土盛がいくつも見える。「何かのまじない?」それともこの地方独特の「農作方法」なのだろうか?そんなことを考えながら岩倉酒造へと向かった。実は、この土盛は「西都原(さいとばる)古墳群」と呼ばれる古墳、つまりお墓なのだそうだ。ここは天孫降臨―神様が天から初めてここに降りて国を創った―の伝説が残りたくさんの神話が生まれた地なのだ。それにしても、こんな風に無造作に特別指定史跡である遺跡が遺されているのは、少々驚いた。それだけ人の手が加えられていないということだろう。千年も前から変わらずこの風景は、ここにあったにちがいない。そして時間だけが静かに流れてきた・・・。一瞬タイムスリップしたような不思議な感覚を覚えずにいられなかった。ふと、ここで焼酎を造る岩倉 幸雄さん、悦子さん夫妻そして娘の幹子さんの、まあるい優しそうな笑顔が思い浮かんだ。もしかすると、太古のゆっくりとした時間がまだここには流れているのかもしれない。あの「笑顔」には、こんな馬鹿なことを思わせる不思議な魅力がある。明治二十三年の創業で、四代目の幸雄さん、妻の悦子さん夫妻の二人で切り盛りしていた。五年前、次女の幹子さんが「弟子入り」し、家族三人で焼酎造りに励んでいる。年間生産石数は僅か二百石(1升ビンで二万本)と、県内の酒造業者の中でも最小規模。『三人が顔を合わせると焼酎の話になる』と悦子さんが言うように、家族三人が輪になって美味しい焼酎をコツコツ造っているお蔵である。宮崎県ほど多種多様な焼酎があり、清酒と焼酎が混在しているユニークな処はない。芋・麦・米・蕎麦・稗(ひえ)・粟(あわ)…などバラエティーに富んでいる。これは江戸時代、宮崎県が七つの領地に分割されていたことに由縁するらしい。薩摩の支配下にあった県南は芋焼酎、西から山ひとつ隔てた人吉藩だった辺りは、球磨焼酎の影響で米焼酎、そして県北は関東武士の多かった延岡藩の影響か清酒が好まれている。岩倉さんも、芋・米・麦の三種類を仕込んでいる。なかでも『芋焼酎に一番精魂を傾けています。』と語るお父さん。実は、芋という原料は結構むずかしい。薩摩芋は生のものしか使えない。保存はきかないし、傷みやすい、品質にバラつきが多い。岩倉さんは「芋の鮮度」を第一に、収穫期の九月〜十一月のみに製造、一回の仕込みも小仕込みにしている。自然の産物だけで造るのが本格焼酎の基本だが、薩摩芋はその最たるものかもしれない。原料にこだわるからからこそ芋焼酎。手がかかるからこそ芋焼酎なのだろう。岩倉さんの焼酎の大きな特徴は「熟成」にある。小分けした瓶・陶器に詰められた焼酎は25%のもので三年以上、最も長いもので三十三年間貯蔵熟成されている。長期熟成が珍しくない現在でも、なかなかこれだけ長期のものは少ない。「長期熟成」というのは、それだけ気の長い話ということだろう。子供を育てるようにじっくり待ってその「子」の個性を引き出す。特に芋焼酎を五年貯蔵した「幹」は、この蔵の傑作といえる仕上がり。岩倉家のまあるい優しい笑顔が、そのまま焼酎になったような、まろやかな口当りだ。蒸留方法は、近年主流の「手軽にまろやかになる」減圧蒸留に流されず。コクがあり、「貯蔵するほどに旨味の増す」常圧蒸留にこだわっている。静かな、ゆっくりとした西都市の時間の中、岩倉一家のもとで焼酎達は、存分にその個性を開花させる。そしてその焼酎造りは、同業者からも『個性的な焼酎造りは生き残りへの手本』と注目を集めている。『父の味を伝えていきたい』という幹子さんの力強い言葉に支えられ、岩倉家の焼酎達は今日も三人の「家族会議」を聞きながら、世に出るのを待っているのだろう・・・・。

|
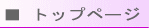 |