■ 藤本酒造ご紹介
「時の流れを感じる本物の熟成酒」
交通の便が悪く地元の方が「陸の孤島」という宮崎県延岡市、そこから車で2時間半程熊本県との県境にある人口2600人の「諸塚村」にお蔵元があります。この村は「九州の屋根」・九州山地の中にあり、諸塚山を中心とする標高1000m以上の山々に囲まれ、椎茸・山菜と渓流で取れる山魚の幸が豊富な村です。お蔵に至る国道509号は、途中から左手は「渓谷」右手は「断崖」となり、譲りあわないと、すれ違えない細い道になります。お邪魔した頃は、清流の所々に「藤の花」が咲き、ホトトギスが鳴く春半ばのころでした。いろいろとお蔵をめぐってきましたがここまで山間に分け入った場所は初めてで、まさに「秘境!」という言葉がピッタリです。こんな空気と水のきれいな場所で醸すお蔵は数少ないでしょう。
もともとは林業で栄えた村で、明治10年創業時のものという藤本本店さんの古い大きな母屋からも華やかだった頃を想像することが出来ます。昭和45年頃までは林業も盛んで、村の人口は2万人以上でした。その後、安い海外の木材の流入のため衰退し現在は過疎の村になってしまいました。お蔵元の藤本毬子さんにお聞きすると、昔は林業に従事する人達は味噌・醤油をすべて自分で仕込んだそうです。その仕込みには焼酎造りと同様に「麹(こうじ)」が必要です。「麹屋」をしているうち、それで焼酎を醸し山で働く人々に販売したことがお蔵の創業だそうです。
「周りから『焼酎を造ってばかりいないで少し売らないかんぞ』とよくいわれます。」と笑いながらお話をしてくださいました。「長く長く寝かせて、旨味・甘味のあるものをゆっくりと少しずつ売っていきたい。あんまり酒をきれいにしないで、そのままが一番喜んで飲んでくれる人達だけでいいんです。」年間生産量100石(1升瓶で1000本程度)という本当に僅かな、たぶん県内でもっとも小さな蔵元さんの一つですが、出荷する全てのお酒が「古酒・熟成酒」です。「やめたら村のみんなに迷惑がかかるから焼酎造りは続けます。自分達が楽しんでやっているから長く寝かせても、価格をあまり上げたくない・・・。」不思議なくらい、ここでは時間がゆっくり流れています。心落ち着かせる、どこか懐かしい風景のなか「藤乃露」は仕込まれているにです。お蔵のなかに入れていただくと、昔ながらの木製の道具の数々が並んでいました。このお蔵は伝承的な「造り」を今に伝えている数少ない造り手なのです。「米を蒸す」ことから「蒸留」まで、「村の焼酎屋」の面影をこれほど強く残したお蔵も珍しいでしょう。特に「麹室(こうじむろ)」はよく掃除が行き届き、「蓋麹」(ふたこうじ・・
・少量の製麹法で手がかかる)による麹造りが行われていました。蒸留機もいたってシンプルな形でしたが、「藤乃露」のやわらかい・香ばしい旨味はこの過程で生まれてくるものなのです。そして、澄んだ空気の中でゆっくりと熟成されていく。 どんなに「昔ながらの製法」や「素晴らしい環境」であろうと結果として「旨い!」でなくては、何の意味もない。焼酎が注目を浴びている今、形だけの「伝承」を売り物にする焼酎が見受けられます。そんな中、このお蔵のお酒「藤乃露」は本当に旨い!そして、その「造りのスタイル」を決して前面に押し出すことなく、お蔵の姿勢がごく自然体なのです。ここにもまた「焼酎造りの原風景」を発見することが出来ました。5年前、杜氏さんが高齢のため引退、現在は息子さんの一喜さんが一人で醸しています。まだ33歳ですが、優しそうな人柄の中に「焼酎造り」への熱い情熱を感じる若手醸造家です。「必ずしも長く寝かせれば美味しくなるとは限りません。酒の出来・不出来が最も大切で、現在では5年熟成が一番良いと考えています。」と語る一喜氏。彼の「造り」に対する真摯な姿勢と強い意志、「藤乃露」が「麦・熟成酒」の銘酒として高い評価を受けることは間違いありません。
 |
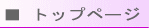 |