■大澤酒造のご紹介
「明鏡止水」のお蔵元、大澤酒造さんは北に浅間山・南に更科山を望む長野県東部に位置する望月町茂田井にあります。平安時代の望月町は朝廷の料馬を育てた御料牧場で、望月という名も八月十五日の満月の日・「望月の夜」に献上されたというところから由来しています。また蔵の前は東海道に次いで諸大名の往来の多かった旧中仙道です。幕末の動乱期、皇女・和宮御降嫁の大名行列、勤皇過激派、天狗党等さまざまな歴史を秘めた街道でもあります。現在もその面影を色濃く残し、お蔵の玄関からのびる白壁の前に立ち、人通りのないそのひっそりとした「たたずまい」の中に浸ると、まるでタイムスリップしたかの様な幻覚にとらわれます。「明鏡止水」を醸す大澤酒造さんは、蓼科山系の良質な水を仕込み水として、恵まれた自然環境を生かし、元禄二年(1689)より酒造業をを始めました。その創業時の酒が白磁古伊万里の徳利に残っており、発酵学の権威・故坂口謹一郎博士によって日本最古の酒と評価された伝統あるお蔵元です。酒名「明鏡止水」とは、一点の曇りもない磨き上げられた鏡と、静かで揺ぎ無い水面ということで「心の中に邪念が無く澄みきった心境」の例えとして用いられます。この酒名には強い思い入れがあり、様々な素晴らしい人との出会いによって生まれ育った経緯があるそうです。現在は、若いお蔵元兄弟が老舗の看板を守り、兄・大澤 真さんが経営を、弟・実さんが杜氏の下で酒造りに精進されています。実さんに、お蔵の酒造りについて伺うと「この酒名に恥じない様に、米の旨味を生かしながら、綺麗で飲み飽きしない酒を醸したいと思って います。毎年が一年生の気持ちで頑張ってゆきます。」とのこと…。『酒はその造り手の人に似る』と言われますが、お二人の真摯な姿勢が酒質に現れる「明鏡止水」は長野県屈指の銘酒といえましょう。
 |
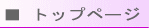 |