■喜多酒造のご紹介
実り豊かな近江米の収穫できる近江の国、湖東平野の八日市で、初代 喜多 儀左ェ門が酒造りを始めたのは、文政3年(1820年)のことでありました。当時は屋号を天満屋と称し、近隣の農家より米を買い付け、酒を造り、八日市の周辺で酒を売っていました。以来、酒造業を代々受け継ぎ、百八十年―昭和23年には法人化し、現在は八代目になります。『喜楽長』という銘柄は、お客様に喜び、楽しく、酒を飲みながら、長生きをしていただけるようにと、念じつつ名づけたとのことであるます。
―喜多 良道 社長のお話―
『酒は美味しもの』『良き酒とは、水晶玉のごとく』38歳の若さで亡くなった私の父親がよく話しておりました。小学生の私には、よくわからない話でありましたが、父親の歳を越え、酒造りを真剣に考える時、心に強く感じる言葉であります。まさに、現在の私ども喜楽長が求めるお酒の姿を示しております。日本の伝統文化の一つである日本酒、その良き姿を守りつつ、高品質で個性ある日本酒を醸し出してまいりたいと考えております。より良き日本酒、喜楽長を求めて日々精進努力することが、私達の生き甲斐であり喜多酒造の変わらぬ姿勢です。
―酒造り一筋40数年 能登杜氏 天保 正一氏のお話―
父親である先代杜氏、天保 勇の酒造りの心と技を継承し、伝統的な能登杜氏の酒造りを頑なに守りつつ、日々技術の向上に精進いたしております。酒造りは、小さな微生物である麹や酵母が活躍してくれます。酒造りに携わる杜氏は、麹や酵母が健全に育ってくれるように、良い生育環境を整えてやることが大切であります。まさに、我が子を育てるがごとく、酒造りを行っております。又、天保杜氏を中心に、ベテランの蔵人と、酒造りを志す若い蔵人たちが、心を一つにして、和をもって美味しい酒を創り出すために日々万進いたしております。
☆ 全国新酒鑑評会において、平成6年、8年、9年(平成7年は休止)金賞を受賞。
☆ 大阪国税局新酒鑑評会では、平成5年、6年、8年、9年(7年は休止)金賞を受賞しています。
 |
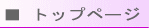 |