■美田のご紹介
『美田』の蔵元・「三井の寿」は、大正11年の創業以来、米と水に恵まれた筑後ならではの酒造りに一貫してきました。蔵沿いに流れるのは小石原川、春になると周り一面、菜の花で埋め尽くされる。ここ三井郡の名の由来は、むかし三つの名水が湧く井戸があったことからその名がつき、江戸時代米問屋だった「三井の寿」が酒造りを始めたのは、運命的ともいえます。そのなかで平成八年に杜氏になった、山下 修司氏は、 『いいワインの条件は、ローカリティ、クオリティ、それにオリジナリティ。日本酒という枠にはめるのではなく、日本酒がワインと同じ醸造酒のワンジャンルと考えれば、絶対地元産の米と水を使わなければならない。つまりその土地ごと・気候ごとに美味しさがある。』として、九州では珍しい「山廃造り」で酒を醸しています。石川県の銘醸「菊姫」で名人杜氏・農口尚彦氏に師事し、伝統の技を受け継ぐ、新進気鋭の若手醸造家で、彼の手によって『美田』は生まれました。「山廃造り」は、昔ながらの手造りの技法で、空気中の乳酸菌を取り入れるため、お酒が出来るまでに一ヶ月近くの時間を要します。彼が、長い時間を擁するこの技法にこだわり続ける理由は原料米にあります。お酒の原料になる品種・山田錦は「酒米の王様」として知られていますが、福岡県はその生産地としては全国第二位の生産量があります。この最高の酒造好適米の旨みを最大限に醸し出すためには、自然の力を生かした昔ながらの『山廃造り』が最適だからです。丹精込めて醸されたお酒は「酸味」と「旨み」が納まった味わい深いものになります。この程よい酸味が、「刺身」から「揚げ物」までどんな料理にもバランスよく合い、その美味しさを2倍、3倍に広げてゆきます。『美田』は日本酒のイメージを変える「食中酒」なのです。福岡の山田錦で造った福岡の山廃『美田』、東京の「嘉多蔵」さんでお楽しみいただければ幸いです。
 |
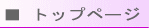 |